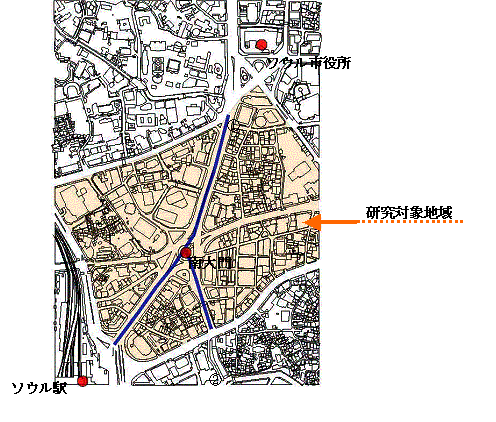3.1. 研究対象地域の選定
ソウル市、特にソウル市中心部には多くの歴史的建造物が散在している。図8に散在する歴史的建造物の一部を示す。
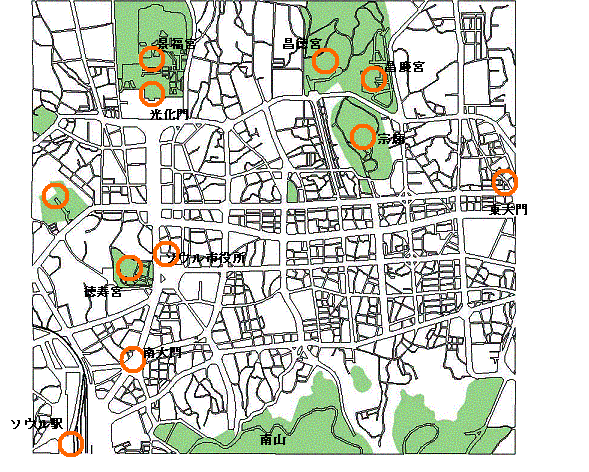
図 8 ソウル市市街地における歴史的建造物

図 9 南大門
南大門は、新首都の正門として、1398年に完成した。その後、数回の改築・補修を加えられ、現在に至っている。特に大きな改築・補修は1448、1479年の改築工事である。このとき南大門は、再建ないしは「新作」といわれるほどの大改築が行われたと考えられる。続いての改築は、南大門の傾頽が著しいための改築工事で、このとき屋根が入母屋から現在みるような寄棟に改造された。南大門の建築は朝鮮半島の城門建築を代表するものといえ、現在、国宝第一号に指定されている重要な建築物である。つまり、観光資源としての側面、景観的な側面、歴史的側面、様々な意味で非常に重要な建築物であるといえる。また、現在、南大門はソウル駅とソウル市役所とを結ぶ幹線道路のほぼ中央に位置し、さらに、南大門市場を脇に控える。
図 10 研究対象地域
3.2. 現地調査について
当初、日本において、可能な限りの研究の基礎資料を収集したが、十分な資料を得ることが出来なかった。そのため、現地調査の実施を計画するに至った。現地調査は研究対象地域の3次元モデル作成に必要と考えられる基礎的資料の収集を目的とした。具体的な調査の目的を以下に述べる。
研究対象地域の地図の入手。
南大門の図面の入手。
南大門のテクスチャの撮影。
南大門を中心にした景観写真の撮影。
研究対象地域の建物高さの調査
研究対象地域の建物テクスチャを撮影。
以上6項目を調査の目的とした。
調査内容は主として写真画像の撮影、収集である。景観写真の撮影に関しては、50mmレンズのカメラを使用し撮影することを原則とした。しかし、テクスチャに関する撮影に関しては、調査日程、カメラの台数、調査員の人数等を考慮し、デジタルカメラでの撮影を可とし、即時、ノート型パソコンにデータを入力しつつ撮影を行うこととした。また、夕刻の撮影は写真の赤焼けを防ぐため、原則として行わないこととした。さらに、各調査員は事前に作成した調査表、調査地図を携帯し、撮影の際、随時、これらへの記入することとした。
調査地図は、現地調査前に最新の地図を入手することができなかった。そこで、現地でこれに替わる最新の地図が入手出来次第、交換、必要事項を書き込み使用することとした。調査表は、事前に作成した仮の現地調査用の地図を元に作成された。調査地図を次頁の図11に、調査表を表2、示す。
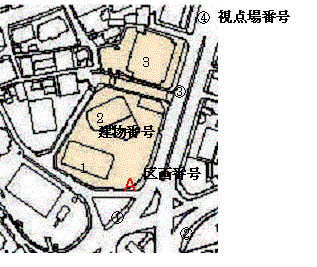
図 11
調査地図
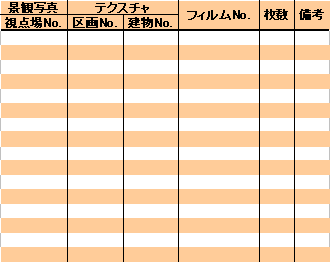
表 2
調査表
現地調査は本研究室のメンバーで構成される3名により行われた。構成された調査員を以下に示す。
教授:佐藤 誠治(Seiji SATO)
学生:李 衡馥(Lee
Hyung Bok、D1) 中野 敏明(Toshiaki NAKANO B4)
調査日程は2000年10月28日から10月31日までの4日間で実施されたが、初日は時間が現地への移動のみに費やされたため、実質3日間という強行日程となった。
調査より得られた資料、データを以下に示す。
最新のソウル市交通地図を入手
研究対象地域周辺のパンフレットを入手。
修理改築の報告書を入手し、南大門の図面を取得。
南大門のテクスチャを撮影。(計9枚)
南大門を中心にした景観写真を撮影。(計37枚)
研究対象地域の建物階数を調査し、データとして取得。
研究対象地域の建物テクスチャを撮影。(計198枚)
調査後、撮影した写真、南大門の図面についてはフィルムスキャナでコンピュータ上に保存した。写真画像は大別して、建物テクスチャ画像、南大門テクスチャ画像、南大門を中心とする景観画像の3種類に分類することができる。建物テクスチャ画像については、これを表に整理した。その一部を次頁の表3に示し、コンピュータ上に保存した写真画像について、代表的なものを以降図12、図13、図14に示す。
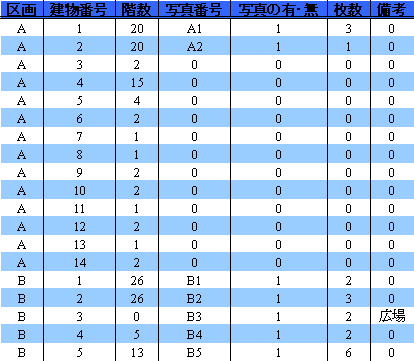
表 3 建物データ

図 12 建物テクスチャ画像 A_01_b
表3について解説すると、区画、建物番号はあらかじめ地図上で決定していた番号である。階数は現地調査で判明した建物に関しての階数であり、写真の有無は、写真画像がデータとして存在するものは”1”、存在しないものには”0”と記入し入力した。データとして入手できた写真画像に関しては画像ファイルの名前として区画、建物番号を組み合わせ、番号をつけ、同一建築物の写真画像が複数存在する場合はaから昇順に番号をつけることとした。つまり、図12の”A_01_b”とはA区画の01の建物の、bつまり2枚目のテクスチャ画像となる。

図 13 南大門テクスチャ画像

図14 南大門を中心とする景観画像
上図に示した写真画像からも南大門周辺に大変高層な建築物が建ち並んでいるのが分り、景観的問題が発生しているのが分る。