5.1. 代替案の考案
先に述べてきた通り、南大門を中心とした研究対象地域の景観は非常に乱れた状態にあり、南大門の存在感、その価値を打ち消してしまっている。これは周辺建築物の無秩序な高層化が、大きな要因となっていると考えられる。
そこで、本研究では、周辺建築物の高さをコントロールしていくための方向性を考えるため、この高さを変化させた代替案を考案し、シミュレーションモデル画像をもとにこれを考察する。
代替案は以下に挙げる、6案を考案した。
高さ60%モデル
建築物の高さを現状の60%に引き下げたモデル。ただし、南大門の高さを下限値としている。つまり、現状で南大門より低層な建築物に関しては、その高さを据え置き、もしくは高さを60%に引き下げた場合の高さを、南大門の高さ以下にしない、ということにした。
高さ80%モデル
高さ60%モデルと同様に、建築物の高さを80%に引き下げたモデル。
高さ120%モデル
建築物の高さを現状の120%に引き上げたモデル。ただし、20階の高さ、モデルでの60.4mをその上限値とする。これは、現在ソウル市において周辺地域における景観整備のため、建築物の高さを20階以下に規制しようとする提案があるためである。
高さ140%モデル
高さ140%モデルと同様に、建築物の高さを140%に引き上げたモデル。
高さ10階モデル
10階を下回る建築物の高さをすべて10階まで引き上げたモデル。
高さ20階モデル
20階を下回る建築物の高さをすべて20階まで引き上げたモデル。
5.2. シミュレーションモデルの構築
研究対象地域において南大門を中心とする景観を考える際、2つの通りが特に重要となる。1つはソウル市役所とソウル駅とを結ぶ巨大な幹線道路で、もう1つは南山に至る道路である。この2つの道路は現地調査、現状モデル構築の際も重点をおいた道路である。ここに計3箇所の視点場を配した。
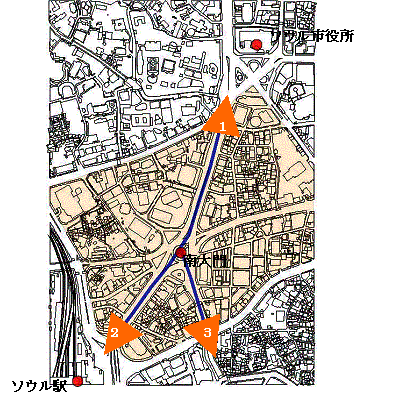
図 50 シミュレーションモデル視点場
視点場の配置は上の図50に示す通りである。
引き続き視点場について、更に詳しく説明する。3つの視点場は、それぞれ研究対象地域の際にあたる部分に配置している。これらの地点は、南大門を中景に望める地点であり、南大門から300〜400m離れた地点となる。近景では南大門が大きな視対象となり、レンダリングした画像は景観といえず、建築物の画像となってしまう。また、遠景では南大門を探さなければ見つからないという状況になる。そこで、南大門を中景に望むこととなる、研究対象地域の端部分に視点場を置いた。また、ソウル市に植栽されている街路樹はその樹高が高く、樹冠が大きい。そのため、歩道から南大門を望むことは非常に難しい。そこで各視点場を車道に設置している。レンダリングの際のカメラは、視野角39.6°、レンズは50mm、カメラの高さを1m50cmと設定した。現状モデルをこれらの視点場から望んだ画像を以下に示す。
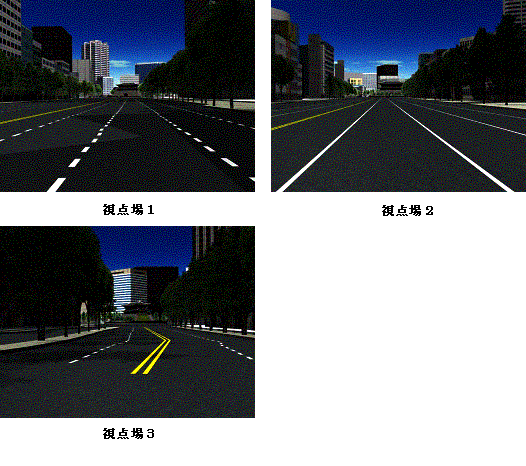
図 51 3視点場からの現状モデル画像
画像からわかるように、南大門を含めた市街地のボリューム感を、非常によく把握することができる。
シミュレーションモデルの構築は、現状モデルをベースに建築物モデルの高さを変化させ、マッピングしているテクスチャに修正を加えることで作成し、前述した3つの視点場より画像を抽出した。次頁の図52、図53、図54にレンダリングしたシミュレーションモデルの画像を示す。
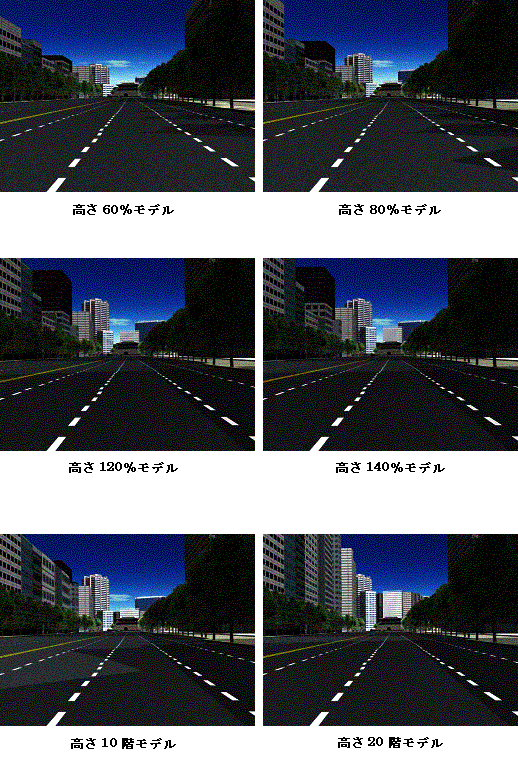
図 52 視点場1シミュレーションモデル
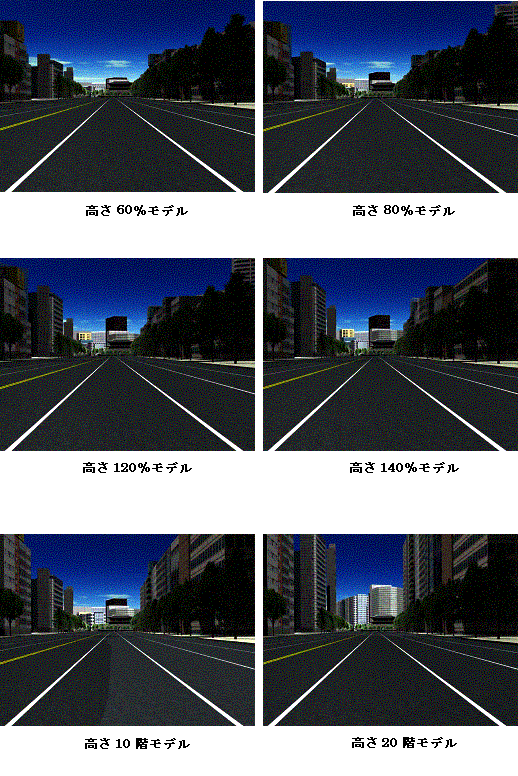
図 53 視点場2シミュレーションモデル
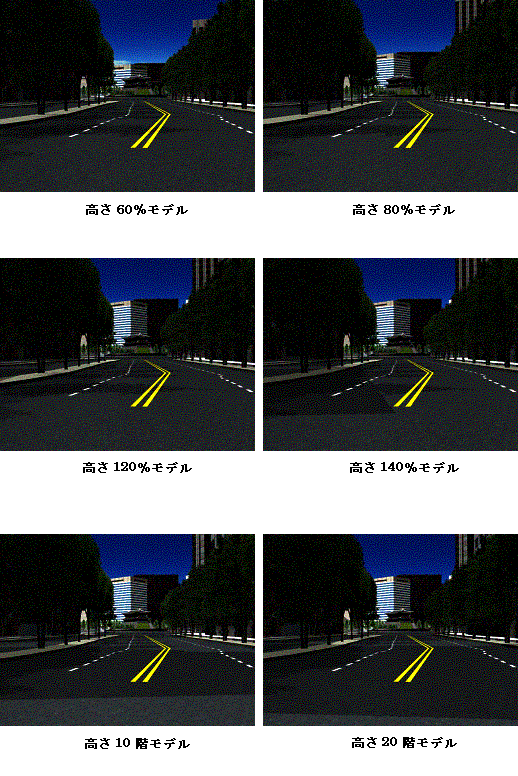
図 54 視点場3シミュレーションモデル
以上、列挙したシミュレーションモデル画像よりその考察を述べる。
視点場1
現状モデル画像から、道路左岸の建築物は比較的低層であるが、右と南大門後方は建築物が高層であることが把握できる。全体的に建築物の高さに統一感がなく、非常に雑然とした印象を受ける。
シミュレーションモデル画像を概観すると、高さ60%、80%モデルに関しては南大門後方の建築物の存在感が薄れるためか、全体的に統一感が生まれ、好感の持てる景観になる。また、高さ120%、140%モデルに関しては現状モデルと大きな違いが感じられない。これは建築物の高さが不統一であり、その印象が非常に強く残るからだと考えられる。高さ10階、20階モデルは建築物が屹立し南大門の存在感は完全に失われてしまっている。
視点場2
現状モデル画像から、全体の建築物が低層で、比較的良好な景観であることが把握できる。
シミュレーションモデル画像を概観すると、高さ60%、80%モデルに関しては南大門後方の建築物がほぼ見えなくなり、ビスタが形成されているのがわかる。逆に、高さ120%、140%モデルは南大門後方の建築物がビスタを破壊し、景観に悪影響を与えていると思われる。高さ10階、20階モデルは視点場1と同様に建築物が屹立し南大門の存在感は完全に失われ、非常に圧迫感を感じる。
視点場3
現状モデル画像から、南大門後方にそびえ立つ建築物が非常に高層である事がわかる。南大門を斜めから望む状態で、存在感が感じられない。
シミュレーションモデルはすべてにおいて、大きな差が見られない。これは、南大門後方にそびえる建築物が、心象に大きな影響を与えているためだと考えられる。この地点における景観の整備は非常に難しいと考えられる。
シミュレーションモデルを通して、それぞれの視点場において代替案の効果に明確な差異が現れることがわかった。3つの視点場の中で、視点場2が一番良好な景観を保持しているように感じられる。高さ60%、80%モデルにおいてよい印象を持ったこと、逆に高さ120%、140%モデルにおいて、良くない印象を感じたことが裏付けになるのではないだろうか。逆に、視点場3においてはほとんどその差が現れなかったことから、すでに高さ制限だけでは景観の整備に効果がない地点が存在することがわかる。
現在、研究対象地域において、建物高さを20階以下に制限するという景観整備の方向性が検討されていると聞くが、本研究を通して、この制限は非常に不十分であると感じた。20階という高さの建築物が屹立すると、かなりの圧迫感を受ける。さらに、南大門は完全にその存在感を喪失させてしまう。また、南大門上方にビスタを形作ることが非常に重要であるとも感じた。例え周囲が低層な建築物で構成されようとも、南大門の背後に高層建築物が存在するだけで非常に良くない印象を受ける。
以上を勘案すると、やはり、周辺地域の高層化には歯止めが必要であると考えられる。特に、南大門後方の建築物が高層化するのは避けるべきありであり、このことを強くふまえた景観の整備が望まれる。