6.1. アニメーションの作成
現状モデル、シミュレーションモデルの計7つのモデルに関してアニメーションを作成した。進路は前述した2つの通りにおいて、3通りの進路を選定した。これを図55に示す。
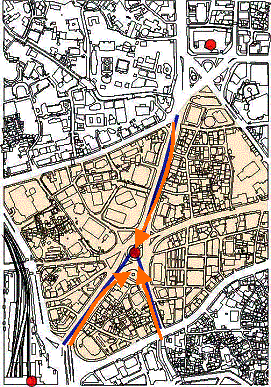
図 55 アニメーション進路
アニメーションは1本が約20秒、これを600フレーム、解像度800×600で出力し、車道を、時速約60kmで移動するよう設定した。レンダリングは3D Studio MAXで行い、未圧縮のavi形式で出力した。ただし、この状態では、1つのavi形式のファイルが800MBを超えるため、再生の際、ハードウェアへの負担が大きく映像が滑らかに再生されない。そこで、TMPGEncでm1v形式のファイルへエンコードしファイル容量を小さくした。結果、合計で21のアニメーションを作成した。例として、次頁図56より、現状モデルにおける視点場1から南大門へのアニメーションを10フレーム間隔で示す。
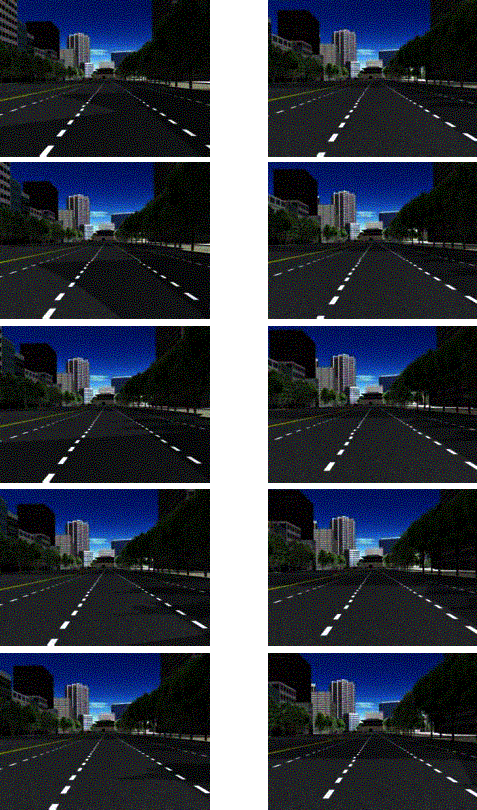
図 56 アニメーション(その1)
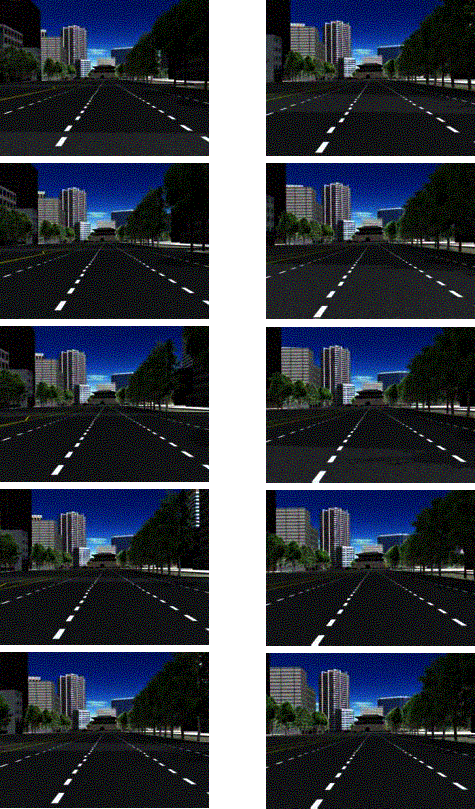
図 57 アニメーション(その2)
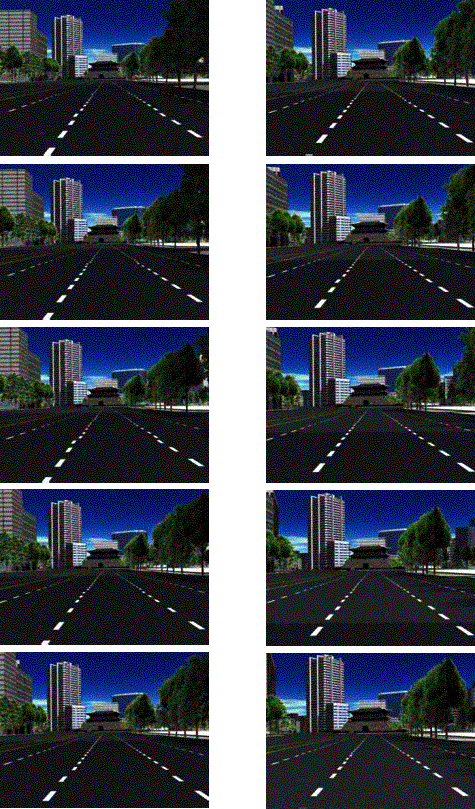
図 58 アニメーション(その3)
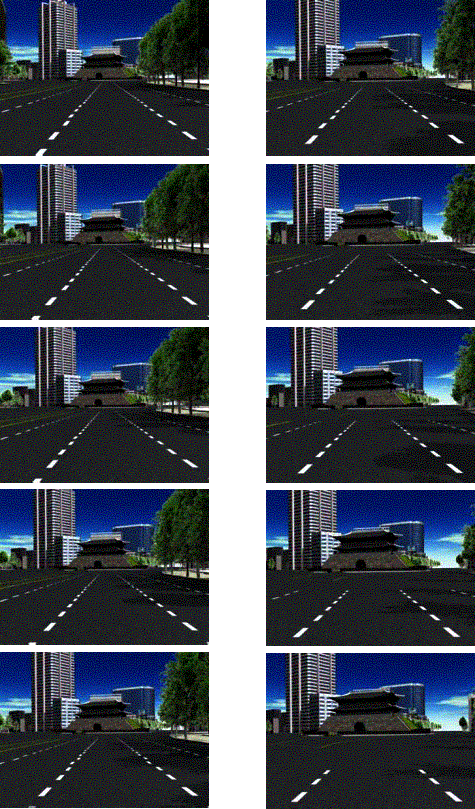
図 59 アニメーション(その4)
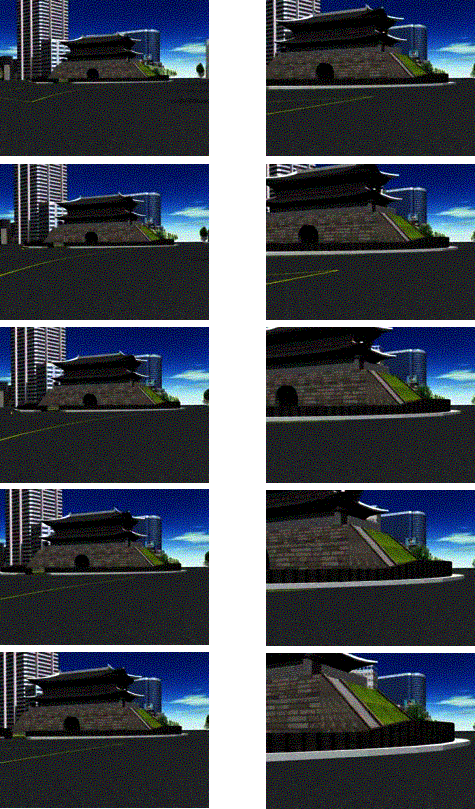
図 60 アニメーション(その5)
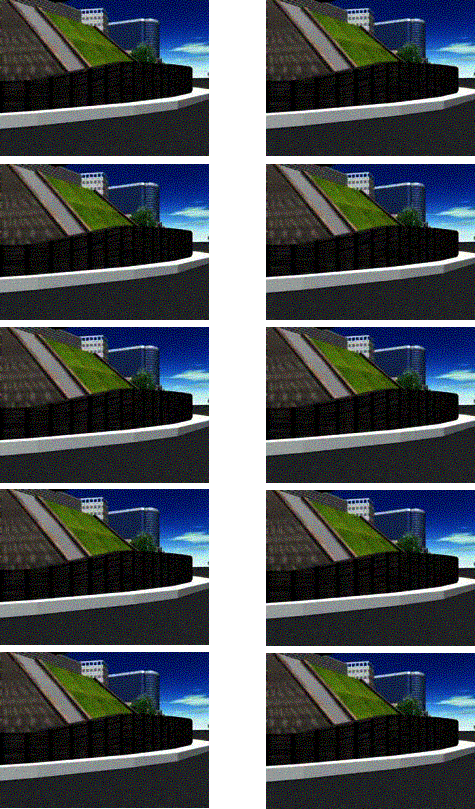
図 61 アニメーション(その6)
6.2. アニメーションによる考察
以上、21のアニメーションを概観しての考察を述べる。
まず、アニメーションを作成することで、研究対象地域をより立体的に把握することができた。静止画像では感じ取れない立体感を確認することには成功したといえるが、それぞれの差異を明確に感じ取れなかったのが実感である。これは、研究対象地域の景観が、すでに充分乱れた状態にあり、一定の割合で高さを一律に変化させたモデルでは、充分な違いが現れないからだと思われる。つまり、高さ10階、20階モデルという、大胆に高さに変化を与えたモデルにおいては、その違いがある程度現れるという結果になったのであるが、その他のモデルにおいてはこれを強く感じることができなかった。
これをふまえると、一定の形式にとらわれない、デザインにまで踏み込んだ、大胆なシミュレーションモデルの構築の必要性が大事であると考えられるが、アニメーションのように、視点場が刻々と変化する場合、特に本研究のように規模の大きな地域におけるアニメーションを作成する場合、これは非常に困難になる。つまり、アニメーションだけでの評価は非常に難しいと考えられる。本研究では、具体的な評価実験は行っていないが、評価実験を想定する際は、静止画、動画の2方向からの評価が必要となるのではないだろうか。
また、アニメーションは視点場の抽出ということに関しては非常に有効な力を発揮すると思われる。これは私見ではあるが、速度をさらに緩めた、低速で動くアニメーションを元に評価、もしくはシミュレーションを行い有効となりそうな、更にいえば、景観を整備しこれが有効に働く可能性のある視点場を抽出し、その視点場において、本研究より更に踏み込んだ代替案を提案、シミュレーションモデルの構築を行い、静止画において評価を行うという手法が望ましいと思われる。