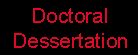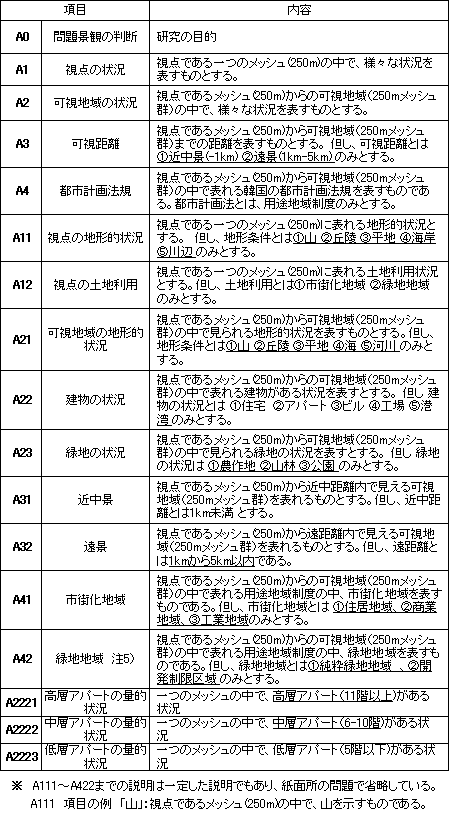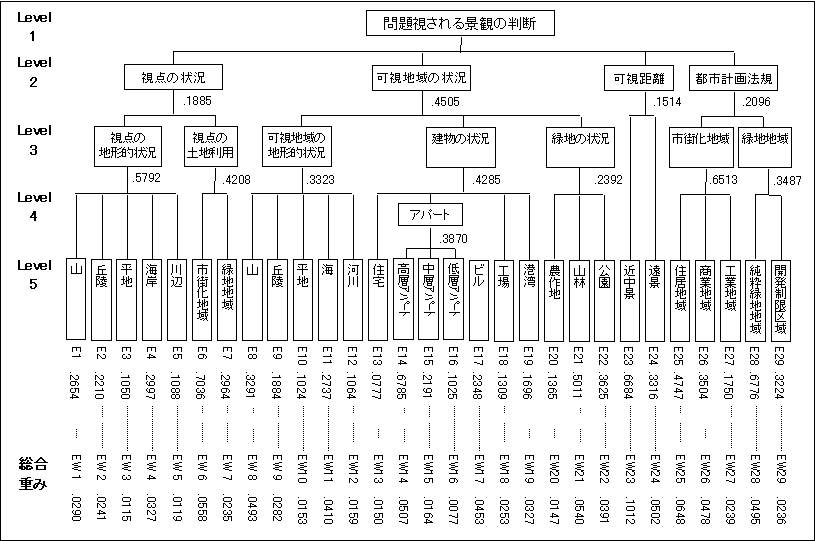|
3-4 エキスパートの知識の合成による判断基準抽出
3-4-1 判断項目の選定と階層図作成
釜山に関する既往研究都市計画・景観関連文献などの資料、および、現地の専門家との議論を通して、景観判断における項目として重要であり、入手可能なデータを考慮して収集する。釜山都市景観を広域的空間スケールでの景観判断という本研究の特質を考慮するために、専門家とのワークショップなどを通して問題景観を客観的に判断できると予測される判断項目を選定した。まず、景観の出現を可能にする対象の空間的構造(対象相互の空間的関係)に力点をおいて捉え、景観の基本関係である「視点」と「視対象」を取り上げる。視点と対象の関係としては、見えがかりの大きさは、一般的に対象まで「可視距離」で表される。そして、都市を構成する基本的な骨格である「都市計画法規」が挙げられ、以上の4つを景観判断の基本要素として選定した。回答者の負担を軽減するため、各項目の定義を詳細に行うとともに、上下関係が認められる要素を予め設定した。項目の内容を表3-4にまとめている。
「問題景観の判断」を目的として、既往の研究を参考にして、エキスパートにヒアリングを行うため、問題景観の判断要因をブレークダウンして作成したものが図3-5の階層図である。この階層図はレベル5までの階層をもつ型であり、ブレークダウンするに従って、同一の評価要素が別々のブロックで現れることが起こった。例えば、A11とA21の下層の評価要素である「山」、「丘陵」、「平地」、「海」、「河川」などの要素が現れ、その要素以後のブレークダウンが同一の構成になる場合である。この場合は、異なるブロック「A1:視点の状況」と「A2:可視地域の状況」で同一の要素構成となっているので、いわゆる「従属性の弊害」は起こらない。評価項目の属性から評価項目の上下関係を把握し、問題景観を明らかにする階層図を作成する。特に、専門家との意見、既往研究から、韓国の地形景観に対しては傾斜地に立地する住居系建築物が最も問題発生の要因と指摘されているため、住居系建物を細分した階層図を作成した。
表3-4 景観判断要素とその内容
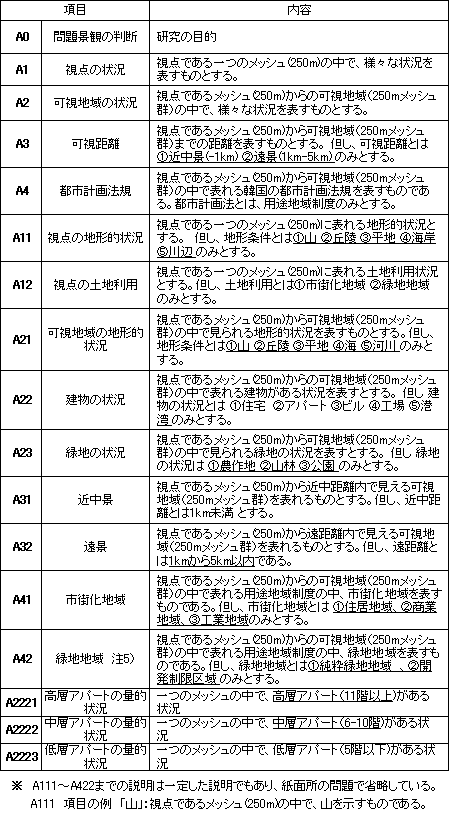
3-4-2 AHP法による一対比較
本システムの構築のため、韓国の研究対象都市である釜山市の景観に詳しいエキスパートにアンケート調査注13)を行い、限定されたデータ及び情報の範囲でエキスパートが釜山に現存する問題景観を判断する際、どのような要素を重要視して判断するのかを明らかにする。分析の方法としてAHP(Analysis
Hierarchy Process=階層分析法)法を用い、最終的に各要因別に重要度を算定した。
今回の調査方法は、評価項目の数も多く、はじめから全員で評価を実施することは、時間の制約上困難であったので、調査票を作成することにした。その構成は ①調査の主旨、②テーマの説明、③一対比較の要領、④評価項目の説明表、⑤評価項目の説明CG、⑥階層図、⑦対象都市の関連資料(CG、写真など)、⑧一対比較の設問と回答欄注10)などであり、分量はA4の16枚となった。一対比較評価の記述はサーティ法による9段階の記述基準を採用した。調査は1998年11月中に行い、釜山の都市景観に詳しい建築・都市計画関連のエキスパート30名に対して、個人もしくは小グループでAHP法の概要、評価項目及びその内容を充分に説明した後に、それぞれが一対比較表を持ち帰りそれに記入してもらう。回収結果、総計28名(建築計画・都市計画関係の大学教授
8名、 建築・都市計画関連の行政担当者 6名、建築士 10名、都市計画関連のコンサルタント
4名)であり、各要因に対して重要度、整合性を求めた。この結果、整合度が0.15以下を有効としたところ、有効なものは回収票28枚のうち、24票となった。最終的にこの24票をAHPによる解析に用いた。
3-4-3 問題景観の判断基準抽出
以上の階層図に沿って、一対比較を行い、AHP法によって各項目の重みを計算する。全体にAHP法による幾何平均を使い、総合評価を算定した。各項目の重みは、図3-5に示す数値である。一番下に書いている数値は、レベル5の項目の累積重みである。累積の重みでは,可視距離の近・中景が0.1012でもっとも高く、都市計画法規の住居地域が0.0648、視点の土地利用の市街化地域0.0558、可視地域の山林0.0540、可視地域の高層アパート0.0507などがすべて高い値を示している。視点の地形的状況としては海岸0.0327、可視地域の地形的状況は山0.0493がもっとも高い。
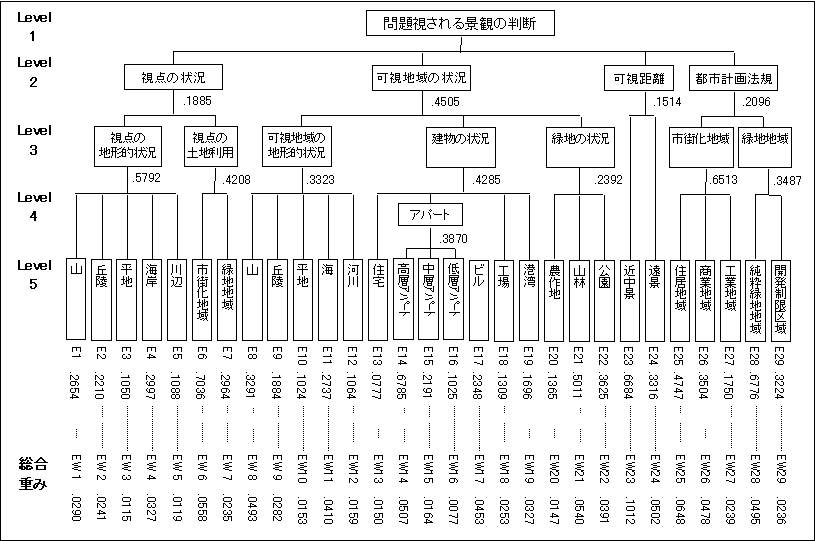
図3-5 階層図と階層における全体的重要度と総合重み
BEFORE
NEXT
|